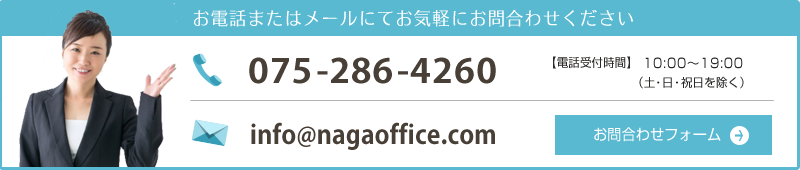お酒にこだわった飲食店では、お客さんが「家でも飲みたいのでボトルを売ってもえないか。」というような要望をされることがあります。
酒販免許がなければ販売はしてはいけないのですが、このような要望が増えてくると飲食の提供だけでなく、お酒の販売もしたいと思うようになるのではないでしょうか?
原則として飲食店ではお酒を販売することはできません。
しかし、ある条件を守ることができれば販売は可能になります。
大きなポイントとしては、酒類を販売する場所が飲食スペースと区別されていることです。
客観的にみて、飲食スペースと酒販スペースがわかれていれば認められることもあります。
店舗のレイアウトや間取りの変更が可能であれば、申請の可能性はあります。
壁をつくったり、個室である必要はありません。客観的にみて分かれていると認識できることです。店舗改装が必要な場合もありますし、レイアウト変更する程度で可能な場合もあります。どの程度で認められるかは店舗設計によりますし、税務署によっても判断が異なりますので、必ず申請前に税務署へ図面を持参し相談してください。
また、スペースだけでなく会計レジや帳簿、納品書なども飲食業とは分ける必要があります。
完全に飲食業と酒類販売業を分けて営業し、一緒にしないということです。
飲食店でのお酒の小売りは、通常よりも厳しい要件が求められます。
まとめると以下の条件を守れる場合には飲食店でも免許が可能になります。
- 飲食スペースと酒類販売スペースを分離し、飲食スペースで酒類の販売は行わないこと。
- 飲食店用と酒類販売用にレジを2ヶ所設けるなど会計を別々にすること。
- 酒類の納品は別々に行い、納品書は飲食店用と酒類販売用を分け、それぞれの納品内容が明確にわかるようにします。また、料飲用酒類については製造元または小売免許業者より、販売用酒類については製造元または卸売免許業者より仕入れます。料飲用酒類を卸売免許のみの業者から仕入れすることはできません。
- 酒類の在庫は飲食用は飲食スペースに保管し、酒類販売用は酒類販売場内に保管し混同しないようにすること。
- 酒類販売用の帳簿を作成し、仕入れおよび販売に関して記帳をおこなうこと。
何度も言うように「販売場所を分けること」が1番のポイントです。
「角打ち」はどういうこと?
時々、「角打ち」みたいにしたいという方がおられます。
角打ちはお酒も売って、飲食もできるというイメージなので特にスペースを分けていないのでは言われます。
実は、角打ちは店内で買ったお酒をお客さんがその場で勝手に飲んでいるだけということです。
いわば、コンビニのイートインスペースのようなもので、店内で買った商品を、自由に食べたり飲んだりできるスペースを置いているだけです。
食べ物も調理したものではなく、缶詰や乾きものなどの加工品を出しています。
角打ちはテーブルなどのスペースを設けているだけで、飲食業ではありません。
飲食業と併設するのが難しい場合は、このように飲食業でない形でお客さんに飲んでもらうことは可能になります。